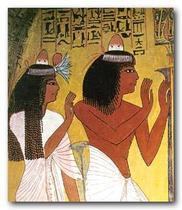★アロマセラピー Aromatherapy ★

まだまだ、暑い日が続くラスベガスですが、 そんな中にも、安らぎ、癒しを感じるひと時を、、、ということで、
LAとラスベガスを行き来されている、かみやま寿里さんにラスベガスの気候に適して、尚且つ簡単に日常に取り入れられる、
「アロマセラピーコラム」を書いていただけることになりました。
毎日の生活にちょっとした一工夫。。。そして快適な時間を過ごしたいと思っている方、是非参考にしてみてください。
LAとラスベガスを行き来されている、かみやま寿里さんにラスベガスの気候に適して、尚且つ簡単に日常に取り入れられる、
「アロマセラピーコラム」を書いていただけることになりました。
毎日の生活にちょっとした一工夫。。。そして快適な時間を過ごしたいと思っている方、是非参考にしてみてください。